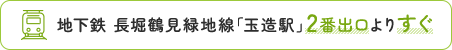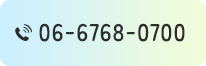胃がんと食道がんの違い
胃がん
胃がんは、胃の壁を覆う粘膜に生じたがん細胞が増殖することで増大したものです。がんが拡大するにつれて、徐々に外側へ進展していきます。がんが胃の壁の外側に到達し、近隣の内臓(大腸や膵臓)や腹腔内にも広がることがあります。
症状
 代表的な症状として、胃の痛みや不快感、違和感、胸焼け、吐き気、食欲不振などが挙げられます。胃がんによる出血で貧血や黒い便が現れ、これが発症のサインとなることもあります。ただし、これらの症状は胃がんだけでなく、胃炎や胃潰瘍でも見られます。むしろ胃がんは初期段階では症状がほとんど現れず、進行しても無症候性でいるケースもあります。食べ物がつかえる、体重が減るなどの症状は進行性胃がんの可能性も考えられます。これらの症状が現れた場合、検診を待たずに速やかに医療機関を受診することをお勧めします。
代表的な症状として、胃の痛みや不快感、違和感、胸焼け、吐き気、食欲不振などが挙げられます。胃がんによる出血で貧血や黒い便が現れ、これが発症のサインとなることもあります。ただし、これらの症状は胃がんだけでなく、胃炎や胃潰瘍でも見られます。むしろ胃がんは初期段階では症状がほとんど現れず、進行しても無症候性でいるケースもあります。食べ物がつかえる、体重が減るなどの症状は進行性胃がんの可能性も考えられます。これらの症状が現れた場合、検診を待たずに速やかに医療機関を受診することをお勧めします。
食道がん
日本人の食道がんの約半数は食道の中央部から発生し、その後、主に食道の下部に生じます。食道がんは、食道内面を覆う粘膜の表面から発生します。また、複数のがんが同時に食道内に発生することもあります。
食道粘膜から発生したがんは、拡大すると外側に広がり、気管や大動脈など周囲の臓器に直接広がります。さらに、食道壁内のリンパ管や血管に入り込んだがん細胞は、リンパ液や血液の流れに沿って移動します。それにより、食道の外側にあるリンパ節や肺、肝臓など他の臓器にがんが転移していきます。
症状
 食道がんは、初期段階ではほとんど自覚症状が現れません。早期発見のチャンスとしては、検診や人間ドック時に行う内視鏡検査が挙げられます。がんが進行すると、飲食時に胸に違和感を感じたり、飲み込むのに苦労したり、体重が減少したり、胸や背中が痛んだり、咳や声がかすれたりするなどの症状が現れます。
食道がんは、初期段階ではほとんど自覚症状が現れません。早期発見のチャンスとしては、検診や人間ドック時に行う内視鏡検査が挙げられます。がんが進行すると、飲食時に胸に違和感を感じたり、飲み込むのに苦労したり、体重が減少したり、胸や背中が痛んだり、咳や声がかすれたりするなどの症状が現れます。
ただし、胸や背中の痛み、咳、声のかすれなどの症状は、肺や心臓、喉などの疾患でも現れます。したがって、食道だけでなく肺や心臓、喉の検査も受けて診断をつけることが重要です。
胃がんの一番の原因
 胃がんの主な原因は、ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)の感染です。 ピロリ菌は幼い頃に感染する菌で、胃の内膜へ侵入すると毒素を放出し、胃内膜に慢性的な炎症を引き起こします。長期間の慢性胃炎により、胃内膜は次第に損傷を受け、胃粘膜の収縮状態である萎縮性胃炎に進展します。これは、がんの発生が非常に促進される状態となります。さらに、ピロリ菌は胃内膜に毒素を直接注入します。 内視鏡検査でピロリ菌感染が疑われた場合は、1週間の内服による治療で完治可能です。(1回の治療で80~90%程度の治癒率)
胃がんの主な原因は、ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)の感染です。 ピロリ菌は幼い頃に感染する菌で、胃の内膜へ侵入すると毒素を放出し、胃内膜に慢性的な炎症を引き起こします。長期間の慢性胃炎により、胃内膜は次第に損傷を受け、胃粘膜の収縮状態である萎縮性胃炎に進展します。これは、がんの発生が非常に促進される状態となります。さらに、ピロリ菌は胃内膜に毒素を直接注入します。 内視鏡検査でピロリ菌感染が疑われた場合は、1週間の内服による治療で完治可能です。(1回の治療で80~90%程度の治癒率)
ピロリ菌以外の原因
ピロリ菌感染以外の胃がんの原因として、生活習慣や自己免疫性胃炎、遺伝子の異常などがあります。遺伝子の異常の有無を確認するには、専門的な検査が必要ですが、自己免疫性胃炎の診断を受けたり、高塩分摂取や喫煙、高血糖などの生活習慣要因に該当したりしている方は、定期的に胃カメラで状態を確認する必要があります。
胃がんと診断されても、早期発見できればほとんどの場合、内視鏡治療で対処可能で、命を落とす心配はありません。
早期がんの切除後からの5年間の生存率は97.3%であり、早期発見すればほとんどの方が完治します。
ただし、バリウム検査では早期の胃がんを見つけるのが困難なため、リスク因子に応じて1〜2年ごとに胃カメラ検査を受けることをお勧めします。
食道がんの原因
 日本では、食道がんの主な原因は飲酒と喫煙とされています。特に、飲酒と喫煙が食道扁平上皮がん(全食道がんの約90%を占めるがん)の発症に繋がる要因となっています。飲酒や喫煙の習慣が両方ある場合、リスクがさらに高まることもあります。
日本では、食道がんの主な原因は飲酒と喫煙とされています。特に、飲酒と喫煙が食道扁平上皮がん(全食道がんの約90%を占めるがん)の発症に繋がる要因となっています。飲酒や喫煙の習慣が両方ある場合、リスクがさらに高まることもあります。
さらに、飲酒中に生成されるアセトアルデヒドという発がん性物質を分解する遺伝子が弱い方は、食道がんにかかりやすくなる傾向があります。具体的には、1滴のお酒でも顔や体が急速に赤くなる方(ホットフラッシャー)がそれに該当します。
「若い頃はお酒に弱く、いつも赤くなっていたが、徐々に慣れて赤くならなくなる」という状態に当てはまっている場合は、リスクが高まっているかもしれません。このような方は、体内にアセトアルデヒドが溜まりやすく食道がんのリスクが高いため食道がんの発症には要注意です。
また、野菜や果物を摂取することは予防において有効です。食生活において、栄養不足やビタミン欠乏も発症要因とされているためです。
一方、日本では食道腺がんは全体の4%しかなく、患者数が少ないため、発生要因がはっきりしていません。その一方で、欧米では食道腺がんが食道がんの半数以上を占め、増加傾向にあります。胃食道逆流症がバレット上皮を形成する下部食道の持続的な炎症の元になるということが分かっています。
そのため、欧米では胃食道逆流症やその原因である肥満、喫煙などが食道腺がんの発生に関係していると言われています。
そのため食道がんを予防するためには、ますは禁煙・禁酒がとても重要だとされています。
胃がん・食道がんの治療
当院では、胃がんや食道がんの早期発見と適切な治療方針の選定を重視しています。
消化器内科として、がんの進行状況や患者様の体調に応じた診療を提供していますが、手術などの高度な治療については提携する専門の医療機関と連携し、最適な治療を受けられるようご紹介いたします。
診断と治療の流れ
胃がんや食道がんの治療は、まずは正確な診断から始まります。内視鏡検査や画像診断を通じて、がんの早期発見を目指し、進行具合を確認します。これにより、適切な治療方針を立てます。
内科的治療
進行が初期段階であれば内視鏡治療で完治を目指せます。また、内視鏡治療の適応がなければ内科的治療として化学療法、放射線療法など、病気の進行の程度や患者様の体調にあわせた治療を検討します。
手術・高度治療
当院では、手術を伴う治療は行っておりませんが、がんが進行している場合や、手術が必要な場合には、信頼のおける専門の提携医院にご紹介させていただきます。
胃がん・食道がんを
早期発見するためには?
近年では検査方法の進歩により、早期に発見される食道がんや胃がんが増加しています。
消化管の検査ですが、主に内視鏡検査が行われます。
上部消化管内視鏡検査では食道、胃、十二指腸を観察でき、微小な変化でも容易に見つけられ、必要に応じて生検(組織の採取)を行い、病理組織診断を行うことができます。その中でも早期食道がんや早期胃がんには、内視鏡でがんの部分だけを切除する内視鏡治療が可能です。この治療法は外科手術と比較して、胸や腹部に傷が残らず、食道や胃の機能を維持しつつ、入院期間も短く済みます。そのためすぐに社会復帰できるメリットも得られます。
胃がん・食道がんに関する
よくある質問
食道がんは転移しますか?
食道の粘膜から発生したがんは、大きくなると食道の外側へと広がっていき(浸潤しんじゅん)、食道の壁を越えて気管や大動脈などの周囲の臓器にまで直接広がっていきます。また、食道の壁内にあるリンパ管や血管にがんが浸潤し、リンパ液や血液の流れに乗って、食道外にあるリンパ節や肺、肝臓などの他の臓器へと移っていきます。
食道がんに前兆はありますか?
食道がんは、通常、初期段階では症状が現れません。しかし、病気が進行すると、食事や飲み物を摂る際の胸の不快感、つかえたような感覚、体重減少、胸部や背中の痛み、咳、声のかすれなどの症状が現れる可能性があります。
胃がんの手遅れの症状は?
胃がんは、初期段階では症状が現れにくいと言われていますが、進行すると、食欲不振や胸やけ、吐き気、背中や胸の痛み、倦怠感などが現れることがあります。
進行するにつれ、胃の消化・栄養吸収の働きが悪くなります。それに加えて、腹水の溜まるスピードが速くなる、腹部が張る感覚、浮腫、排尿障害、吐血や下血による貧血、タール便などの症状が出ることもあります。スキルス胃がんに関しても、大まかに同様の症状が見られることがあります。
なお、「末期がん」の基準ですが、厚生労働省は「治癒を目指した治療に反応せず、進行性かつ治癒困難である、または治癒不可能と医師が総合的に判断した場合」と定義しています。
スキルス胃がんとは何ですか?
スキルス胃がんは胃がんの約10%を占めるがん疾患です。通常の胃がんとの違いは、胃壁の内部に病巣が進行しやすいことです。このため、スキルス胃がんは早期発見が難しく、発見されると進行がんであることがほとんどです。また実際に、スキルス胃がんを指摘された患者様の60%以上に転移が認められています。
胃がんは治りますか?
一昔前まで、胃がんは日本の国民病とも呼ばれていました。しかし、年々その死亡率は減少傾向にあり、現在、早期に発見された胃がんは非常に治癒率が高く、5年生存率は90%を超えています。
しかしながら、胃がんが進行してステージ4になると、5年生存率は10%を下回ります。このことからも分かるように、早期発見と早期治療が極めて重要であるとされています。